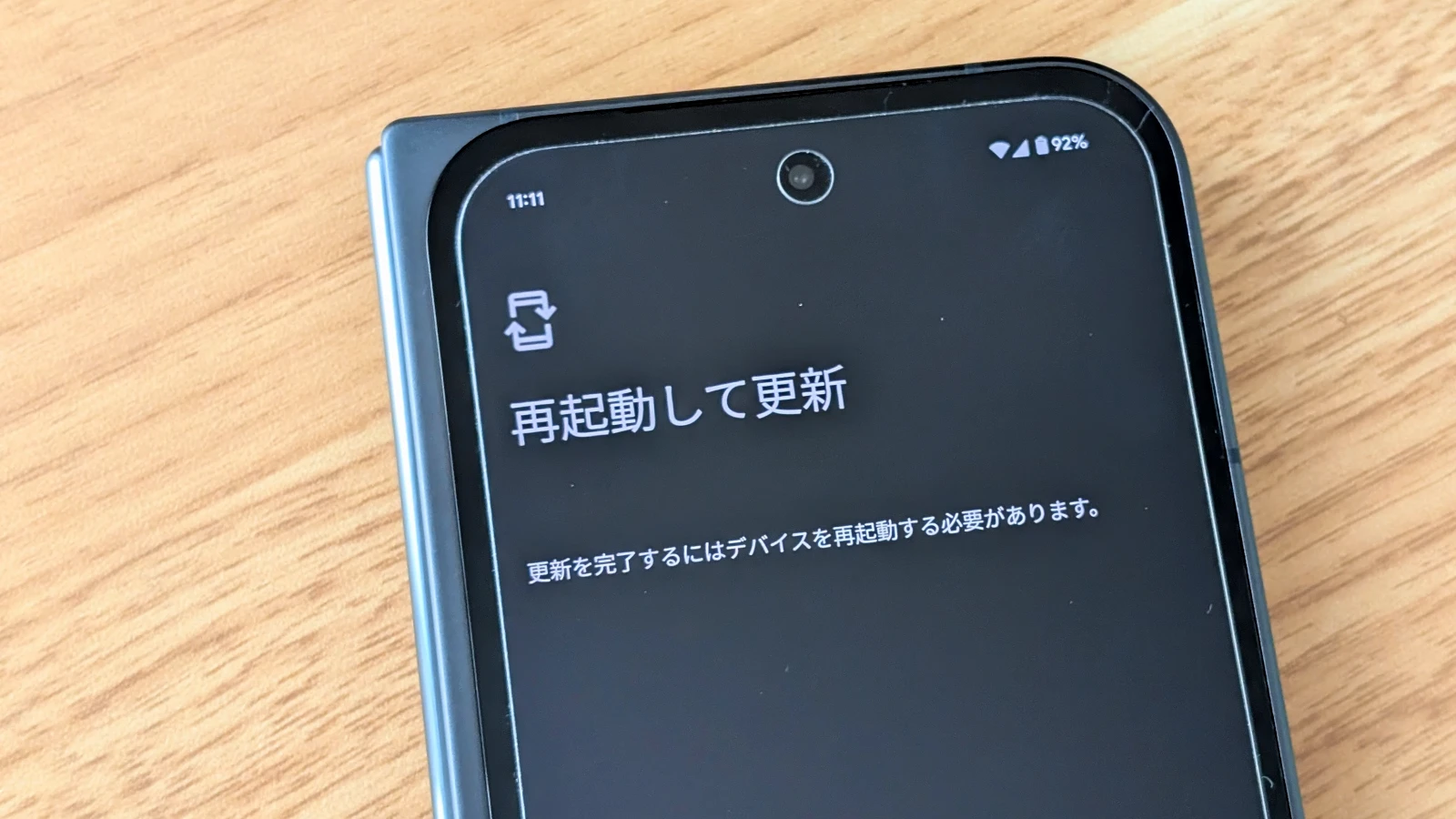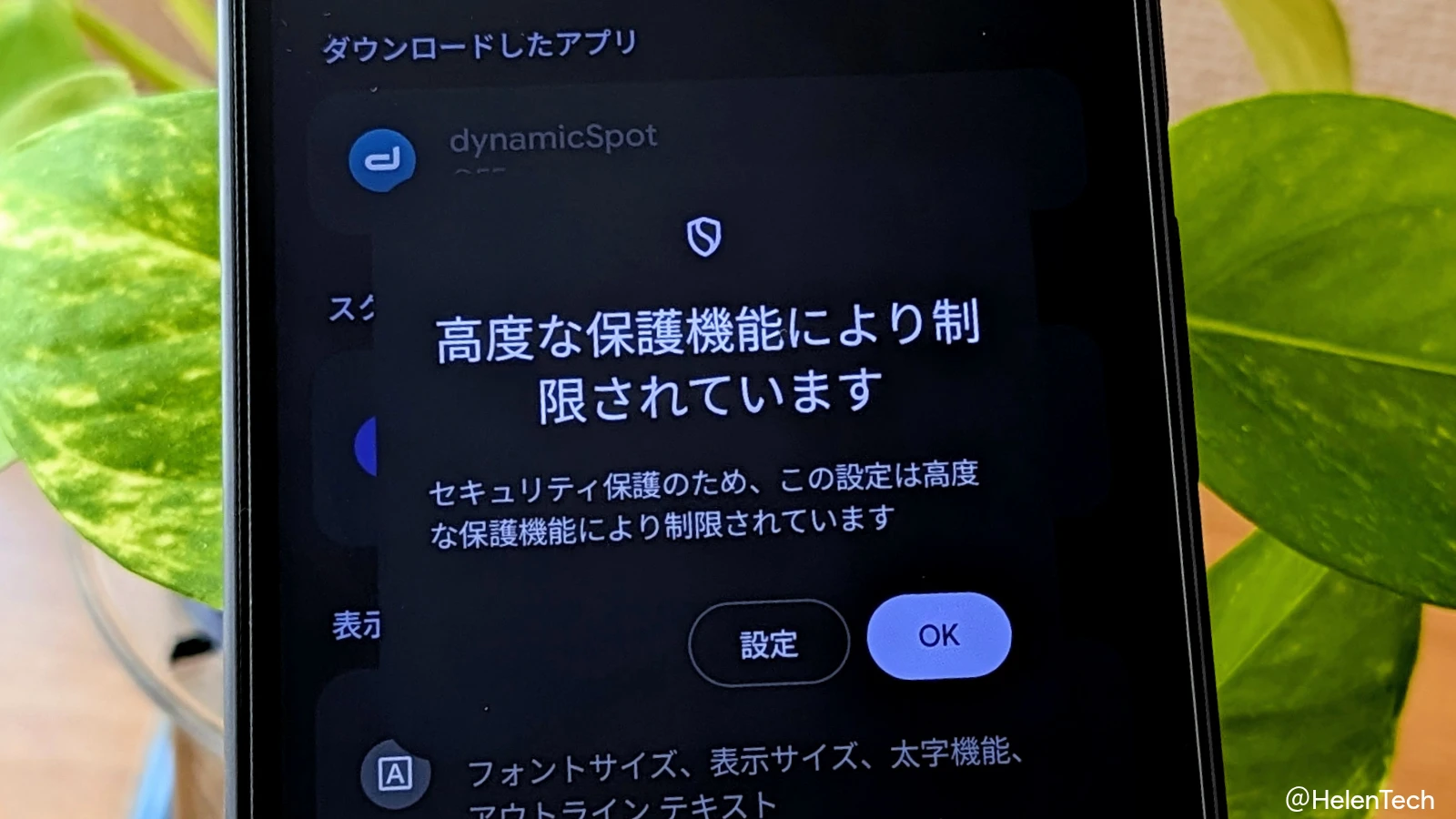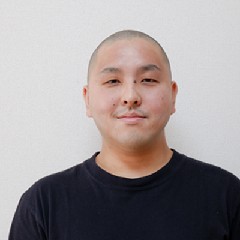Samsung が次期フラッグシップモデル「Galaxy S26」シリーズに含まれる予定の「Galaxy S26 Edge」の開発を中止し、薄さを追求した「Edge」シリーズを廃止する方針であると、韓国メディアの Newspim が報じました。
これは今年 5 月に発売された「Galaxy S25 Edge」の販売台数が、期待を大幅に下回ったことが主な理由とされています。
この報道が事実であれば、2025 年 1 月に開催が見込まれる Galaxy S26 シリーズの発表イベントでは、従来の「Plus」モデルを含む 3 モデル構成(S26 Pro, S26 Plus, S26 Ultra)に戻る可能性が高まりました。
わずか 5 か月での方針転換、期待外れの販売台数
Newspim の報道によると、Samsung は「Edge」シリーズの廃止を決定し、その方針を社内にも通達したとされています。今年 5 月 23 日 に大々的に発表された「Galaxy S25 Edge」でしたが、発売からわずか 5 ヶ月 での方針転換となります。
販売不振は深刻なもので、Hana Financial Investment のデータによると、8 月 までの累計販売台数は他のモデルと大きな差が開いたことが確認されています。
- Galaxy S25 Edge: 131万台
- Galaxy S25: 828万台
- Galaxy S25 Plus: 505万台
- Galaxy S25 Ultra: 1,218万台
これまでシリーズ内で販売台数が最も少ない傾向にあった「Plus」モデルと比較しても、「Edge」モデルの販売台数は 4 分の 1 程度にとどまりました。
すでに生産された「Galaxy S25 Edge」は、在庫がなくなり次第、追加生産は行われない見込みです。
「Edge」が受け入れられなかった要因
Newspim が業界関係者筋の話として伝えたところによると、Edge モデルが市場に受け入れられなかった理由として、いくつかの点を指摘されています。
- バッテリー容量への懸念: 超薄型化を追求した結果、バッテリー容量が 3,900mAh にとどまり、ユーザーが期待するバッテリーの持続時間を満たせなかった可能性があります。
- 中途半端な価格設定: 「Galaxy S25」(256GB / 115 万 5000 ウォン) よりも高価で、「Galaxy S25 Ultra」(256GB / 169 万 8400 ウォン) よりは安価という価格設定(256GB / 149 万 6000 ウォン)が、魅力的に映らなかった可能性があります。
- 限定的な需要: 多くのユーザーが大画面スマートフォンに求める価値は、必ずしも「薄さ」だけではなかったと考えられます。大容量バッテリーや、価格と性能のバランスといった実用的な要素がより重視された結果と言えます。
また、ある関係者は「Edge シリーズは、そもそも競合他社(Apple)が薄型モデルを開発しているという情報に対抗するために投入された側面がある」と指摘しており、市場の真の需要を見極めた上での製品ではなかった可能性も示唆しています。
Galaxy S26 シリーズのラインナップはどうなる?
今回の報道により、Galaxy S26 シリーズのラインナップは、当初の計画から変更されることが確実視されています。
以前は、「Plus」モデルを廃止して「Edge」モデルに置き換える計画や、両方を展開する 4 モデル構成の可能性も報じられていました。
- 関連記事:
しかし、今回の決定により、再び「Plus」モデルが復活し、以下の 3 モデル構成に戻る見方が有力です。
- Galaxy S26 Pro (仮称)
- Galaxy S26 Plus
- Galaxy S26 Ultra
報道によると、急な方針転換に Samsung 社内でも混乱が広がっており、タイトな開発スケジュールにプレッシャーがかかっているとの声も聞かれます。
なお、「Galaxy S26 Edge」自体はすでに開発が完了しているため、将来的に別の形で発表される可能性は残されています。
日本市場への影響は限定的か
これまで日本では、Galaxy S シリーズの「Plus」モデルや、今回話題となった「Edge」モデルは正式に販売されていません。
そのため、仮にグローバルでのラインナップが 3 モデル構成に戻ったとしても、日本市場では従来通り、標準モデルと Ultra モデルの 2 モデル展開が継続される可能性が高いと考えられます。その場合、日本のユーザーにとっては直接的な影響はほとんどありません。
Samsung の今回の決定は、技術的な挑戦よりも市場の現実的な需要を優先した戦略的な判断と評価できます。薄さという付加価値が、バッテリーの持続時間や価格といった実用的な要素を上回れなかったという事実は、今後のスマートフォン開発の方向性にも影響を与えるかもしれません。
出典: Newspim, Android Authority