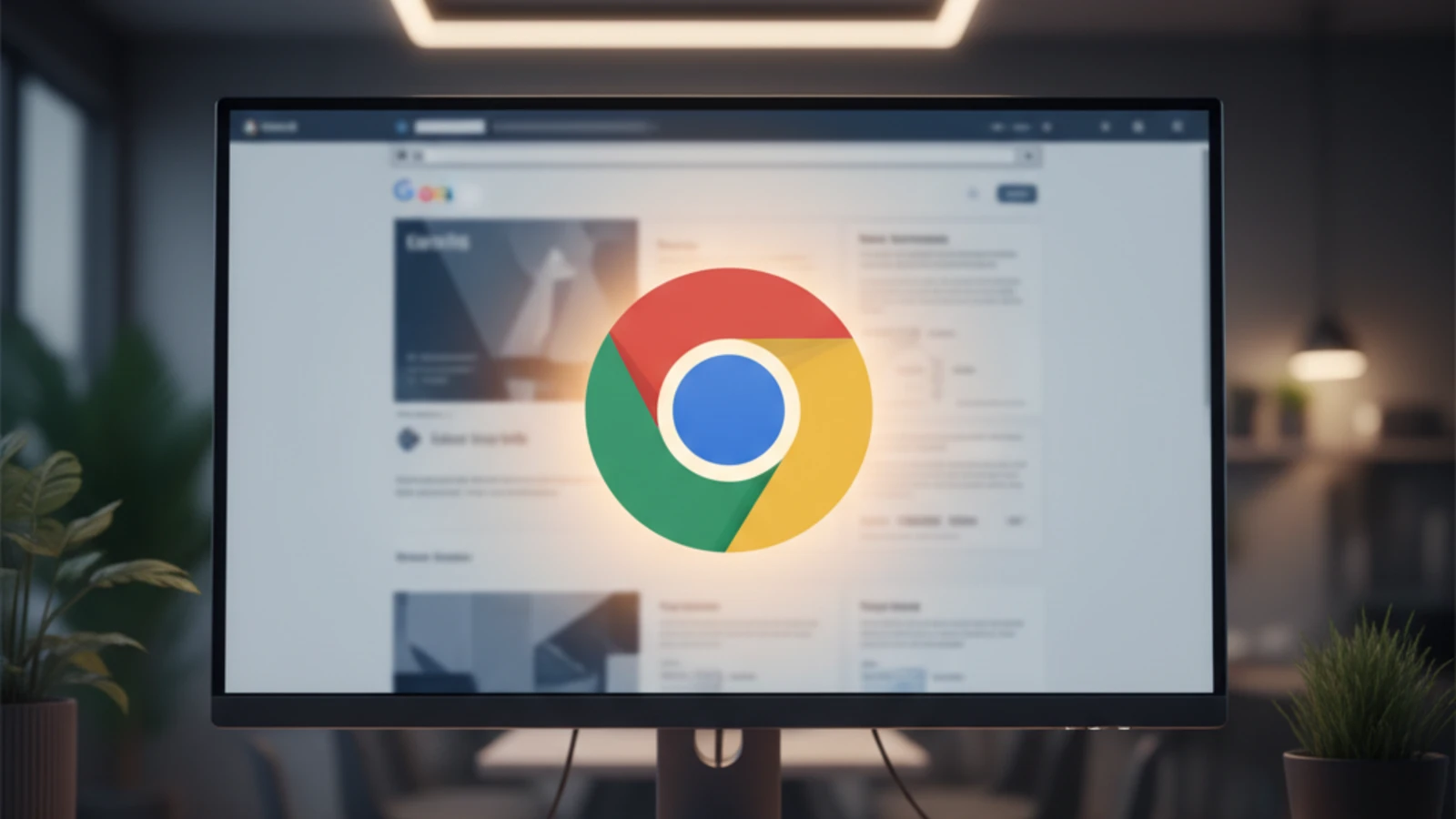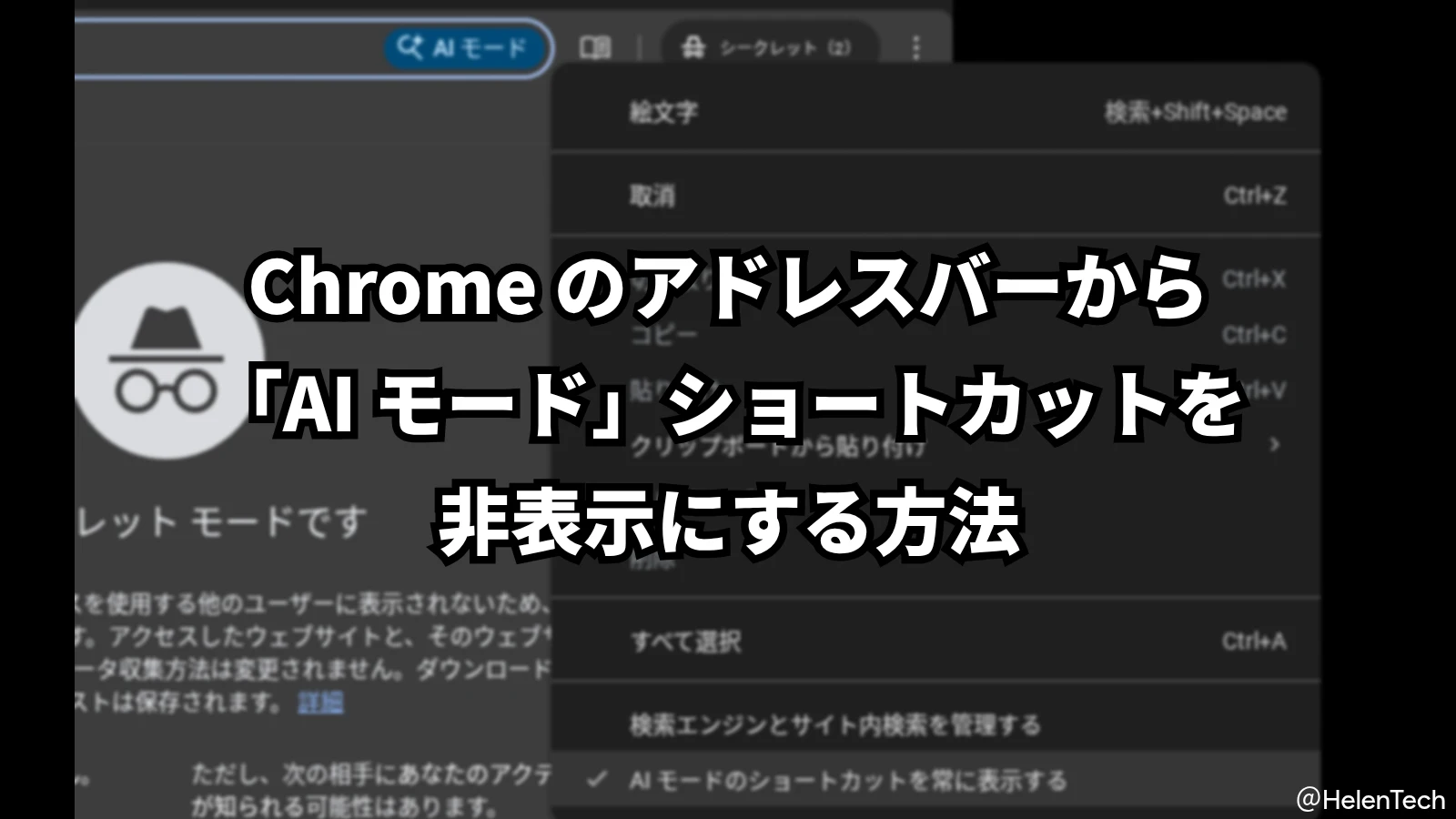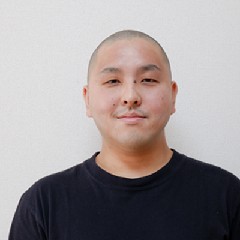Google は Chrome 向けに、Web サイトがユーザーのデバイス性能を把握できる新たな API「CPU Performance API」を提案しています。この機能により、処理能力に応じた動作調整が可能になりますが、ユーザー追跡への懸念も指摘されています。
デバイス性能をもとに Web 表示を自動調整
「CPU Performance API」は、端末の CPU 性能に関するおおまかな情報を Web サイト側に提供することで、処理負荷の高い機能の制御や表示内容の簡略化を可能にします。
この API は、すでに Chrome に導入されている「Compute Pressure API」(CPU 負荷の使用率を示す)と連携して利用することが想定されています。
主な目的は以下の通りです。
- 処理の重いコンテンツ(ゲーム、ビデオ通話など)をデバイス性能に合わせて制御
- 不要な演算を抑え、バッテリー消費を削減
- 開発者が、端末スペックに応じて最適化を施しやすくなる
今後この API が実装された場合、ChromeOS や Android デバイスでもリソースに応じた Web 表示制御が一般化する可能性があり、Chromebook ユーザーにも影響が及ぶかもしれません。
デバイス特定につながるリスクも
一方で、こうした情報が外部サイトに共有されることで、フィンガープリント(個別端末の特定)につながる可能性があり、プライバシーの観点から慎重な対応が求められます。
Google はこれまでも、ユーザーの操作状況(アクティブかどうかなど)をサイト側に通知する機能を提供しており、今回の提案も同様に情報共有の範囲を広げるものとなります。
現時点では以下の状況となっています。
- 提案日:2025年10月6日
- ステータス:Chromium プロジェクト内の初期提案。マイルストーン(導入時期)は未定
- ブラウザ対応:Firefox、WebKit、Web 開発者コミュニティからはまだ反応なし
- 担当:Blink > Performance APIs チーム
「CPU Performance API」の導入が進めば、表示内容や機能がデバイスの性能に応じて動的に変化するようになります。ただし、利便性向上とプライバシー保護のバランスをどう取るかが、今後の検討課題といえそうです。
関連する Chrome の最近の動向
Chrome ではこのほかにも、以下のような改善が進められています。
- Snapdragon 搭載 Windows デバイス向けにグラフィック処理を強化
- Chrome の新しいタブページで検索ボックス(Realbox Next)の新デザインをテスト中
- Google レンズによる動画ソースの自動表示機能
- Web 通知のワンクリック解除ボタンをデスクトップ版で試験運用
出典 : Windows Report, Chrome Platform Status